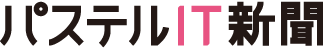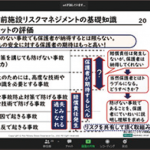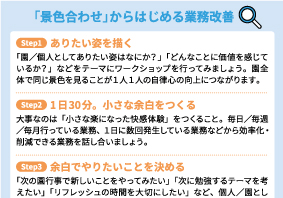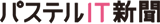この記事のポイント
- 子どもの姿が出発点。教育観や学びの場を見つめ直す「イエナプラン教育」
- 日本初のイエナプランスクール認定校として開校した大日向小学校の実践
- イエナプラン教育を保育現場に導入。子どもの幸せを追求するグローバルキッズ経営者の思い
教えるのではなく自ら学ぶ環境構成
大日向小学校があるのは長野県南佐久郡佐久穂町。人口1万人ほどの小さな町で、廃校となった小学校の校舎を再活用して2019年に開校しました。
「誰もが、豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる」を建学の精神に掲げる同校の軸となっているのが、1924年にドイツで生まれオランダで広まったイエナプラン教育です。「すべての人がかけがえのない存在であり、教育はその一人一人の個性や内的な力を自分らしく発達させることであり、学校はそこに集まった異なる者同士がお互いに学び、成長し合う場である」。教育学者であり哲学者でもあるペーター・ペーターセンにより提唱されたのは、実践的な指導法ではなく人間観や教育観、そして学校という学びの場の捉え方でした。

その環境構成の特徴の一つが異年齢学級です。異年齢のため、できる・できないは違って当たり前。他者との比較や競争ではなく自分自身に目を向けやすい環境をつくります。大日向小学校では1・2年生、3・4年生、5・6年生が同じ教室で過ごし、取材に訪れたこの日もお互いに教え合ったり助け合ったりする姿が見られました。
時間割は教科で区切らず、「対話」「遊び」「仕事(学習)」「催し」の4つの活動で構成。週末のできごとや特定のテーマについて話し合うサークル対話からはじまり、ブロックアワーと呼ばれる時間で子どもたちはグループリーダー(教師)から提示された1週間分の学習課題をそれぞれ自分のペースで計画立てて進めます。

そして、イエナプランの核となっている活動が、子どもたちが協働で探究するワールドオリエンテーションです。「めぐる1年」「技術」「コミュニケーション」「共に生きる」「わたしの生」「環境と地形」「つくること・使うこと」の7領域からグループリーダーがテーマを決め、子どもたちは思い思いに問いを立て、対話を通じて広げ、1~2か月かけて学びを深めます。
「今は1・2年生は歯、3・4年生は氷、5・6年生は民主主義について探究している。子ども自身の問いから始まる探究は面白いですよ」と話すのは、久保礼子校長です。学習の合間には指先や身体を使った「遊び」の時間があり、週の終わりには「催し」として学んだことを発表。リズミカルに1週間が構成されています。

「違いを認め、対話で解決することを大切にし、その上で自分で考え選択し生きていく。大日向での日々で自分で考える習慣や主体性が育ち、責任ある自由を学んでいく」と久保校長。
こうしたイエナプランの考え方に、全国から多くの保護者が期待を寄せました。開校から6年、現在、大日向小学校に通う児童のほとんどが移住者。学びの場を共につくるという同校の思いに共感する保護者や地域住民も多く、農園や養蜂場、畑を開放したり、学習に使う機織機や蜂の巣を提供したりと、積極的に参画。保護者主催の授業や防災サークルもあるそうです。
久保校長は、「保護者も子どものありのままを受け止める教職員に期待してくれている。信じて進めるのはそこに子どもの育ちが現れているから」と確信を得ています。

保育現場に広がるイエナプラン
自立と他者との共生を具現化するイエナプランの考え方に共感し、同校を設立した株式会社グローバルキッズの中正雄一社長は、イエナプラン教育をグローバルキッズグループの保育・学童施設で2025年4月から導入することを決めました。

「イエナプランは乳幼児の保育・教育の考え方とも合致する。発達段階が異なる中で、大日向小学校では子どもたちの比較対象は常に自分に向かっている。お互いを尊重し、自分らしく過ごす姿が見られた」と中正社長。就学前の段階においても、子どもが大人に依存するのではなく、子どもが自ら考え、行動し、表現できるようになることを思い描いているといいます。導入に手を挙げた施設長も、「子どもの主体性とグローバルシティズンシップを目指せるイエナプランに期待している」と語りました。
これまでの保育・教育の良さを取り入れつつ、新たな挑戦がはじまりました。
学校法人茂来学園大日向小学校
長野県南佐久郡佐久穂町にある日本初のイエナプランスクール認定校。自立・共生をコンセプトに、子どもと教職員、保護者、地域住民が一体となって学びの環境をつくっている。全国から入学希望者が集まっている。