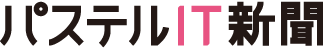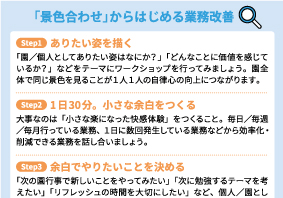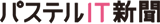今の自分の生活からは考えられないことですが、両親が昭和51年に港北幼稚園を開園させた頃、学生であった自分には、将来、幼稚園の仕事を受け継ぐことに抵抗感が強く、できるならば違う仕事の道に進みたいと強く思っていました。
紆余曲折があって、その後、自園の幼稚園を引き継ぐことになるのですが、そのときに大きく影響を受けたのが、教員免許を取得するために大学に編入して、様々な人や保育と出会う形で学んだ幼児教育の奥深さでした。
時期はちょうど平成元年の幼稚園教育要領の大改訂の頃です。「幼稚園は小学校の下請け機関ではない」「子どもは遊びの中で育つ」「子どもの主体性を大事にする」など、幼児教育とは、大人が望ましいと決めたことを子どもにさせることではなく、もっと子ども自らが育つことを支えていく教育であることが法的に整備されたのです。また自分の意識としても、幼児教育はやりがいのある仕事なんだと、霧が晴れていくように、園にかかわることに抵抗感が消えていったのです。
とはいえ、自園の保育は一斉活動を中心にミニ小学校的でした。その保育を遊びを中心とした保育に変えていくことは、それほど容易ではありませんでした。保育者にも保護者にも何度も保育を変えていくことの意味を丁寧に説明して、実際に育った子どもの姿からわかってもらう努力が必要でした。いま、架け橋のプログラムに注目が集まっています。小学校以上の教育が子ども主体に変わっていくためにも、幼児教育に学ぶべきことは多いと思っています。
港北幼稚園/ゆうゆうのもり幼保園(神奈川県) 園長 渡辺 英則 先生
学校法人渡辺学園 港北幼稚園、認定こども園ゆうゆうのもり幼保園 園長。幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会委員、全国認定こども園連絡協議会副会長。